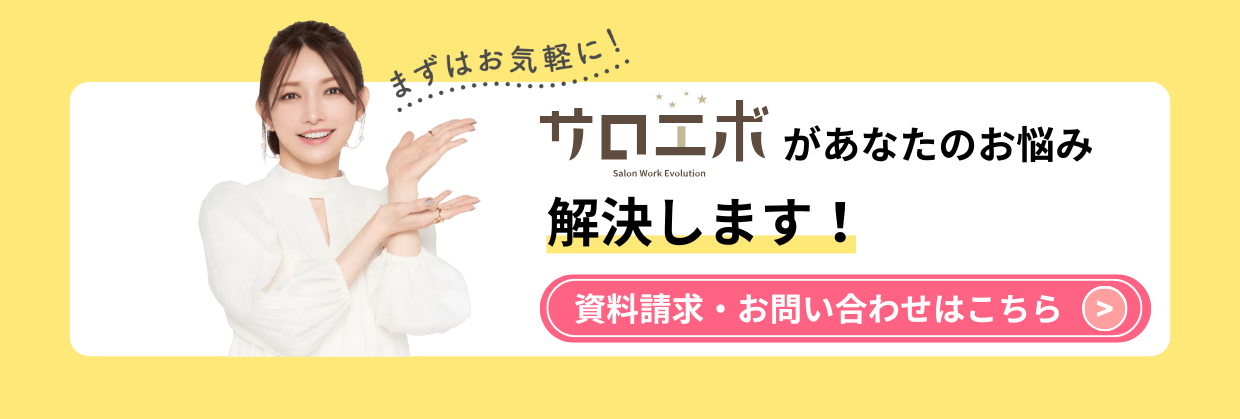厚生労働省の「令和5年度衛生行政報告例の概況」によれば、2023年度末現在で、美容所は27万4,070施設に達し、1995年以降増加傾向が続いています。
激しい競争環境に置かれているなか、さらに経営状況を圧迫しているのが、原材料費や人件費の高騰による適正価格の見直しです。
コストが上昇した場合、本来であれば価格を改定しなければいけません。
しかし、多くの美容室が価格改定の必要性を感じながらも、お客様の反応への不安や競合他店との価格競争を懸念し、なかなか踏み切れないのが現状です。
そこで重要になるのが、値上げの適切な進め方です。値上げによる影響を完全に避けることは困難ですが、適切に対応することで顧客離れのリスクを抑え、経営の安定化を図ることが可能になります。
この記事では、値上げの背景から適正価格の決め方、実施のタイミング、告知方法まで、失敗しない価格改定の進め方を解説します。
美容室が値上げを迫られる3つの背景
 多くの美容室が値上げを迫られている主な要因は以下の3つです。
多くの美容室が値上げを迫られている主な要因は以下の3つです。
- 材料費・光熱費の高騰による粗利率の悪化
- 人材不足・賃上げ・インボイス制度に伴う人件費の高騰
- 低価格路線の限界と技術レベルの維持にかかるコスト増
それぞれ詳しく解説していきます。
材料費・光熱費の高騰による粗利率の悪化
サロン経営において、まず注目すべきは材料費と光熱費の上昇です。
ここ数年、シャンプーやカラー剤、トリートメントといった基本的な薬剤の仕入れ価格がじわじわと上がっています。
原材料費の高騰、輸送コストの増加、円安といった複数の要因が重なり、従来と同じ品質の商品でも、仕入れコストは確実に上昇しているのが現状です。本来であれば、コスト増は価格に反映されるべきですが、実際は値上げに踏み切れないまま、経営者の手元に残る利益が年々削られるという厳しい状況が続いてしまいます。
日本政策金融公庫が2023年11月に発表した調査によれば、「仕入れ価格が上がった」と回答した企業は全体の82.7%、理容業で65.6%、美容業でも58.0%と過半数を超えています。さらに同調査では、仕入れ価格の上昇が経営を悪化させていると答えた企業は89.4%にのぼり、価格転嫁が追いつかない実態が浮き彫りになっています。
実際、前年より販売価格を引き上げた企業は全体の55.2%に達し、前年度よりも19.7ポイント上昇しています。一方で、美容業・理容業では「価格を据え置いた」とする回答が60%を超えており、値上げの必要性を認識しながらも、消費者の反応を懸念して踏み出せない現状が見てとれます。
参考:価格動向に関するアンケート調査結果|日本政策金融公庫
人材不足・賃上げ・インボイス制度に伴う人件費の高騰
今、美容室経営において深刻な課題となっているのが、人件費の上昇です。
中でも、スタイリストやアシスタントの人材確保がますます難しくなっており、多くの店舗が人手不足に頭を悩ませています。働き方においても、フリーランス志向の高まりにより、長期的に雇用を継続することが難しくなってきている現状があります。
そのため、技術のある人材をつなぎとめるには、以前よりも高めの給与設定や、労働条件の柔軟さが必要とされています。
さらに、2025年度(令和7年度)には最低賃金の大幅な引き上げが予定されています。厚生労働省の中央最低賃金審議会が取りまとめた答申によると、全国平均は時給1,118円となり、前年度より63円の増加となる見込みです(※引き上げ幅としては過去最大)。この改定により、パートやアルバイトを含めた全スタッフの人件費が、今後さらに増えることが確実視されています。
加えて、インボイス制度の導入も経営に少なからず影響を与えています。例えば、外部スタッフや業務委託者への報酬支払いについて、適格請求書を発行できない事業者への支払いでは消費税の仕入税額控除ができなくなったため、美容室側の実質的な負担額が増加しています。
また、適格請求書の発行や処理の手間が増え、税務管理の複雑化や事務負担が増えたことで、会計ソフトの導入や顧問税理士との契約を新たに結ぶ店舗もあり、間接的なコスト増に直結しています。
低価格路線の限界と技術レベルの維持にかかるコスト増
美容室の営業戦略として、かつては「低価格・短時間・大量集客」のスタイルが一定の成功を収めてきました。
新規開業時には、周辺店舗との差別化や集客効果を狙って価格を抑えることも重要でした。しかし、その路線を長期的に続けることには限界があることを、多くの経営者が実感し始めています。まず、低価格であればあるほど、1人あたりにかけられる時間やコストが限られるため、接客や技術に十分な余裕を持てなくなります。
予約の詰め込みや回転率重視の営業は、スタッフの疲弊を生み、施術クオリティのばらつきやミスの原因にもなりかねません。結果として、リピーターが定着しづらくなり、集客のために広告費や割引を重ねるという悪循環に陥ることもあります。
さらに、美容室の技術力を高め、維持するためには、それ相応の時間と費用をかけた教育や研修が必要です。新しい技術や薬剤、トレンドに対応するには、外部セミナーの受講、練習用ウィッグの購入、講師を招いた社内研修など、見えにくい投資が重なります。
たとえば、1回数万円にのぼる技術講習を定期的に受けさせている店舗も多くあります。しかし、価格を据え置いたままでは、継続的な人材育成に必要な資金を確保するのが困難になります。お客様は価格だけでなく、「この人に任せたい」と思える安心感や満足度に価値を感じています。
持続的に高いレベルのサービスを提供するためには、適正な価格設定が不可欠です。
美容室の値上げ試算と価格設定
 値上げを検討する際に、多くの美容室経営者の方が次のような悩みを抱えています。
値上げを検討する際に、多くの美容室経営者の方が次のような悩みを抱えています。
- どのくらい価格を上げれば適正になるのか
- どのメニューにどれだけ価格改定を反映すればよいのか
- 利益を確保しつつ、お客様に納得していただける価格はいくらなのか
上記の悩みに対して、感覚ではなく具体的な数字をもとに判断する方法をご紹介します。適正な価格設定により、経営の安定化とお客様への誠実な説明の両立が可能になります。
目標利益率から逆算して適正価格を設定
価格を改定する際は、最初にどの程度の利益を確保したいのか、目標を明確にすることが必要です。漠然とした値上げではなく、具体的な数値を根拠に価格を設定することで、お客様は納得し、安心して受け入れることができます。
売上高総利益率(粗利益率)
まず基本となるのが、売上高総利益率(=粗利益率)です。これは売上から原価を差し引いた利益が、全体の売上に対してどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。
計算式
売上高総利益率(%)=(売上 − 原価) ÷ 売上 × 100
たとえば、カット+カラーのメニューが6,000円で、原価(材料費など)が2,400円かかっていた場合、粗利益は3,600円、粗利益率は60%になります。美容室の場合、この粗利益率が60〜70%程度を目安とすると、適切な価格帯を維持しやすくなります。原価の上昇が粗利率を圧迫している場合には、それに応じた価格調整が必要です。
営業利益率
次に注目したいのが営業利益率です。こちらは、材料費以外にかかる家賃・人件費・光熱費などの費用をすべて差し引いた後に、どれくらい利益が残るかを見る方法です。
計算式
営業利益率(%)= 営業利益 ÷ 売上 × 100
※営業利益 = 売上 − 原価 − 一般管理費(家賃・人件費など)
この数値が10〜15%以上あれば、経営は安定しているといえます。もし10%を下回っている場合は、経費を見直すか、価格の再設定が必要になる可能性があります。
経常利益率
講師業やSNSを通じた副収入がある場合は、経常利益率にも注目しましょう。
これは本業以外の営業外収益や費用も含めた、より総合的な利益指標です。
計算式:
経常利益率(%)=(営業利益 + 営業外収益 − 営業外費用) ÷ 売上 × 100
セミナー出演や物販収入がある場合、それも含めて利益率を算出します。ここで注意したいのは、この利益率が高すぎる場合、本業である美容サービスが十分な利益を出せていない可能性があるという点です。
これらの指標をもとに、目標利益率から逆算して価格を決定することが、持続可能な経営に欠かせません。あらかじめ想定した粗利率や営業利益率を達成するには、各メニューごとにどれくらいの価格が必要なのかを試算しておくことが重要です。
例えば、原価が3,000円、利益を2,000円確保したい場合、最低価格は5,000円以上になります。さらに、人件費や家賃の比率も考慮すると、もう少し上乗せした価格が「適正」と判断できるようになります。こうした計算を行うことで、お客様への説明にも説得力が生まれ、自信をもって値上げを実施できるようになります。
段階的な値上げで価格を設定
美容室が価格改定を行う際、多くの方がお客様の反応、特に長年通ってくださっている常連の方々に対して、突然大幅な値上げをすることに対して懸念を抱かれます。
この不安を解消し、効果的に価格改定を進める現実的な方法として有効なのが、段階的な値上げです。段階的な値上げによって、初回の値上げ後、来店数、リピート率、顧客満足度などの数値を検証でき、その後の戦略を冷静に判断できるためです。反応に大きな変化がなければ、次の調整へ進む判断が容易になります。
また、価格を段階的に見直すことは、単なる値上げではなく、サービス全体の質を向上させる機会と捉えることもできます。例えば、価格改定に合わせて施術をより丁寧に行ったり、マッサージやカウンセリングの時間を充実させたりすることで、お客様に価格以上の満足感を提供できます。
このように料金上昇とサービス向上が連動していれば、お客様の理解も得やすくなります。何より大切なのは、「なぜ値上げを行うのか」という背景をきちんと伝えることです。
材料費の上昇や人件費の見直し、スタッフ育成への投資など、美容室を持続的に運営していくための努力を、言葉にしてお客様へ届けることは、信頼関係の構築にもつながります。
メニュー個別と一括値上げの利益率を比較して設定
価格改定を行う際、すべてのメニューを一律に引き上げるべきか、それとも原価の高いメニューだけに絞って値上げをすべきか。この判断に迷う方は少なくありません。
ここでは、メニューごとの個別値上げと一括の値上げ、それぞれの特徴と利益率への影響について整理してみましょう。
まず、メニュー個別での値上げは、施術ごとの原価や利益率を分析し、採算が合っていないものから順に見直す方法です。ブリーチや縮毛矯正などは材料費や施術時間が長く、他のメニューに比べて原価率が高くなりがちです。対象のメニューだけを値上げすることで、必要な部分にだけ焦点を当て、無駄のない価格改定が可能になります。
お客様に対しても、「高コストな施術のみ価格調整を行いました」という説明がしやすく、納得も得られやすい傾向があります。
一方で、メニュー全体を一律に見直す「一括値上げ」は、価格表をすっきりと保ちたい場合や、サービス全体の価値を底上げしたいときに適しています。例えば、全メニューを5%ずつ引き上げることで、店舗全体の利益構造を改善することができます。この方法は計算がシンプルで、施術間の価格バランスも保ちやすく、スタッフにとってもオペレーションが分かりやすいという利点があります。
どちらの方法にも一長一短があるため、最も大切なのは、自店舗の数字を把握したうえで、適切な選択をすることです。施術ごとの原価率、施術時間、人気度、リピート率といった指標をもとに、まずはメニューごとの採算性を一覧にして可視化してみましょう。
そのうえで、収益性の低いメニューには重点的な見直しを行い、全体的な印象を損なわない範囲での一括調整を組み合わせると、バランスの良い改定が実現できます。
美容室の値上げに最適なタイミングと判断基準
 価格改定を成功させるためには、どのくらい上げるかだけでなく、いつ上げるかも極めて重要です。適切なタイミングは以下のとおりです。
価格改定を成功させるためには、どのくらい上げるかだけでなく、いつ上げるかも極めて重要です。適切なタイミングは以下のとおりです。
- 材料費の原価率が20%を超えている
- 地域の料金相場を見て値上げタイミングを判断
- 顧客離れを最小化するなら閑散期の値上げが有効
それぞれ詳しく解説していきます。
材料費の原価率が20%を超えている
美容室の価格改定を考える上で、まず確認しておきたいのが「原価率」です。
一般的な美容室の原価率は10~20%と言われています。使用する薬剤や商材、道具の仕入れ価格が、販売価格に対して20%を超えた場合、人件費や家賃、光熱費といった経費を差し引いた際に、赤字化するリスクが高まります。実際、近年では美容商材だけでなく、さまざまな業界で原材料費の高騰が続いています。
帝国データバンクの調査によると、2023年には100ブランド中、4割が前年から値上げを実施し、その理由の多くに「原材料価格の上昇」や「輸送費・包装資材の高騰」「円安による輸入コスト増」などが挙げられています。美容業界も同様に、これらの影響を避けることはできません。
参考:2023 年「ブランドコスメ」価格改定動向調査|株式会社帝国データバンク
こうした背景から価格改定を行う際には、まず「仕入れ値の上昇によって価格を見直さざるを得ない状況にある」という事実を、正直にお客様に伝えることが重要です。隠すのではなく、丁寧に説明することで、誠実さが伝わり、理解を得られやすくなります。
地域の料金相場を見て値上げタイミングを判断
価格改定を検討する際は、自店の立地エリアにある競合サロンとの価格バランスを考慮することが重要です。自店の原価が上昇したとしても、周囲の価格帯から大きく外れると、お客様に違和感や不信感を与えてしまう可能性があります。
まず、同じエリアで同じ客層をターゲットにしている店舗の料金表を調べましょう。特に、カット・カラー・パーマなどのメニューの価格帯やセットメニューの構成に注目してください。ホットペッパービューティー、Googleビジネスプロフィール、公式ホームページなどを活用すれば、地域の相場を比較的簡単に把握できます。
その際、単に平均価格を見るだけでなく、その価格に見合ったサービスがなされているかを確認することが重要です。 例えば、他店より高めの価格設定でも、丁寧なカウンセリングや高品質な薬剤の使用といった付加価値があれば、お客様はその価格に納得して選ぶ可能性があります。
また、周囲のサロンが価格改定を実施する時期を見計らい、自店もタイミングを合わせる戦略も有効です。他店が値上げを開始している中で自店だけが旧価格を継続していると、かえって価格に対する不信感を生むことがあります。逆に、相場の動きと歩調を合わせることで、自然な形で新しい価格を受け入れてもらいやすくなります。
顧客離れを最小化するなら閑散期の値上げが有効
株式会社リクルートの調査では、美容室の価格改定が最も多く行われたのは10月で、次いで1月、12月と続いています。
この傾向から、秋から年初にかけてのいわゆる閑散期が、値上げのタイミングとして現場で実際に多く採用されていることが分かります。
また、同調査によると、値上げが行われたメニューで最も多かったのはカット、次いでカラーでした。カットやヘッドスパに関しては500円未満の値上げが最も多く、それ以外のメニューでは500〜1,000円未満の価格改定が主流となっています。これらのデータからも、小幅で段階的な価格改定が中心であり、顧客の心理的負担を軽減する工夫がなされていることがうかがえます。
参考:美容サロンの価格改定に関する調査<ヘアサロン編>|株式会社リクルート
閑散期は、予約に余裕があるぶん、お客様一人ひとりに丁寧な説明をする時間を確保しやすく、万が一反応があった場合も早期に気づくことができます。加えて、価格改定にあわせてサービス内容の向上や施術メニューの改善をセットで打ち出すことで、新しい価格に納得してもらいやすくなります。
値上げ後の客離れを防ぐフォロー施策
 価格改定後、お客様に継続してご来店いただけるかどうかは、実施前後の対応にかかっています。そのため、以下の点に注意しましょう。
価格改定後、お客様に継続してご来店いただけるかどうかは、実施前後の対応にかかっています。そのため、以下の点に注意しましょう。
- 早めの告知と丁寧な理由説明でお客様の理解を得る
- サービス向上による付加価値を提供する
- 独自メニュー開発で他店との差別化を図る
それぞれ詳しく解説していきます。
早めの告知と丁寧な理由説明でお客様の理解を得る
まず最も大切なのは、値上げの決定をなるべく早い段階で告知することです。
値上げ直前の告知では驚きや不信感を招くことがあるため、できれば1ヶ月以上前からの告知を目安に準備を進めましょう。お知らせは店内ポスターや口頭でのご案内だけでなく、LINE公式アカウント、SNS、予約アプリなど複数のチャネルを活用することで、認知の幅が広がります。
告知時には、価格改定の理由を丁寧に説明することが不可欠です。例えば、原材料費の高騰、人件費の見直し、よりよい商材への切り替え、スタッフ教育への投資など、店舗として努力を重ねた結果の判断であることを伝えると、お客様も納得しやすくなります。
特に、常連のお客様に対しては、一人ひとりに直接説明する時間を設けると、より深い信頼関係が生まれます。
サービス向上による付加価値を提供する
価格を見直す際には、サービス内容の見直しも同時に行うことが有効です。
付加価値の向上があることで、価格だけが変わる場合と比べて、顧客の納得感が高まりやすくなるためです。例えば、既存の施術時間を少し延長してより丁寧なカウンセリングを行う、マッサージの時間を充実させる、アフターケアのアドバイスをより詳しく提供する、といった追加コストをかけずにできるサービス向上が効果的です。
お客様一人ひとりにかける時間と丁寧さが向上することで、メニュー内容や使用する薬剤を変えなくても、従来以上の満足度を実感していただけるようになります。価格改定を「サービス品質向上の機会」として捉え、お客様により価値のある時間を提供することが重要です。
独自メニュー開発で他店との差別化を図る
価格改定と同時に、他店との差別化を意識したメニュー開発も重要です。特に近年注目されているのが、髪質改善メニューの導入です。
HOT PEPPER Beautyのフリーワード検索ランキング(2024年10月時点)によれば、「髪質改善」は10代から40代の女性の間で上位を占めており、幅広い年齢層にニーズがあることがうかがえます。髪質改善に特化したサロンが台頭するなど、売上アップに直結しやすいカテゴリーと言えるでしょう。
参考:ホットペッパービューティー フリーワード検索ランキング|株式会社リクルート
また、SNSにおける髪質改善の動画投稿も増加傾向にあり、Before→Afterの比較や、艶やかな髪に櫛を通す映像などが視覚的なインパクトを与え、集客力を高める要素として機能しています。動画は短尺であるほど視聴されやすいため、SNSとの親和性も高く、視覚情報の強みを活かした発信が可能です。
HOT PEPPER Beautyでも、該当プランを活用すれば動画投稿機能を利用できるため、こうした発信と組み合わせることで、価格改定後の集客施策として活用が期待されます。一方、男性向けではパーマ需要が伸びています。2023年時点で男性のパーマ利用率は13.7%と、女性の8.6%を上回る結果が出ています。
特に「ツイストスパイラル」など具体的なデザインが検索されており、情報ニーズの高さが伺えます。20代に次いで30代の利用者も多く、職場でのカジュアル化やジェンダーレス化など社会的背景も、パーマの浸透を後押ししています。
このように、ニーズの高いメニューやトレンドを取り入れ、他店では提供されていない付加価値を作ることで、価格改定の納得感が生まれやすくなります。顧客層に合った独自性のある施術を磨くことは、価格以外の要因で選ばれるサロンづくりに直結します。
サロエボで値上げ前後の売上・顧客データの分析を効率化
 価格改定の前後で顧客の動向や売上の変化を正確に把握し、判断材料として活用する方法を解説します。サロン専用の予約・顧客管理システム「サロエボ」を活用することで、感覚ではなく数字に基づいた経営判断が可能になります。
価格改定の前後で顧客の動向や売上の変化を正確に把握し、判断材料として活用する方法を解説します。サロン専用の予約・顧客管理システム「サロエボ」を活用することで、感覚ではなく数字に基づいた経営判断が可能になります。
売上データと顧客分析で値上げ効果を可視化
価格改定の結果を把握するには、値上げ前後の売上や来店数の変化を具体的に記録し、比較していくことが大切です。
サロエボの分析機能を使えば、日々の売上や客単価、リピート率といった基本的な数値を簡単に確認できるため、価格改定が業績にどのような影響を与えたかを整理しやすくなります。例えば、値上げ後に新規顧客がやや減ったとしても、リピーターの来店単価が上がっていれば、全体としての売上は上がっている可能性があります。
逆に、予約のキャンセルが増えているようであれば、告知やサービス内容の見直しが必要かもしれません。このように、数字に注目することで、感覚では見落としがちな変化を捉えることができ、次の方針を検討する材料となります。
来店履歴・施術データから顧客傾向を分析
価格改定を成功させるためには、どのメニューが支持され、どの顧客層がどのくらいの頻度で利用しているかを把握することが不可欠です。
これらの情報は、日々の来店履歴や施術データとして蓄積されています。
サロン専用の分析ツール「サロエボ」を活用すれば、これらのデータを効率的に分析できます。サロエボは、来店回数、施術履歴、リピート傾向などをグラフで視覚的に表示するため、勘や経験だけでなく、データに基づいた判断が可能になります。
例えば、来店頻度の高いメニューや特定の年齢層に人気の施術など、顧客の傾向を把握することで、値上げ後の不安を最小限に抑えたメニュー設計が可能です。さらに、期間ごとの変化も追跡しやすく、対策の効果を即座に確認できることも大きな利点です。
施術の質を維持しながら価格戦略を検討する上で、こうしたツールの活用は強い味方となります。数字を味方につけることで、より納得感のある判断と改善に繋がり、成功へと導くことができるでしょう。
まとめ
価格改定を成功させるには、どのメニューが支持されているのか、どの層のお客様がどのくらいの頻度で通っているのかを把握することが重要です。これらの情報は、日々の来店履歴や施術データにしっかり蓄積されています。
こうしたデータを効率よく分析できるのが、サロン専用の分析ツール「サロエボ」です。サロエボでは、来店回数や施術履歴、リピート傾向などをグラフで直感的に確認できるため、勘や経験だけに頼らない判断が可能になります。
例えば、来店頻度の高いメニューや特定の年齢層に人気の施術など、顧客の傾向を把握することで、値上げ後の不安を最小限に抑えたメニュー設計ができます。さらに、期間ごとの変化も追いやすく、施策の成果をすぐに振り返ることができるのも大きな強みです。
施術の質を保ちながら価格戦略を練るうえで、こうしたツールの活用は心強い味方となります。数字を味方にすることで、より納得感のある判断と改善が可能になるでしょう。